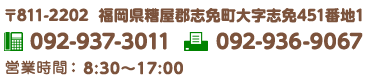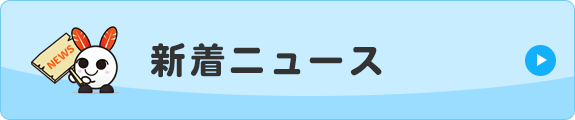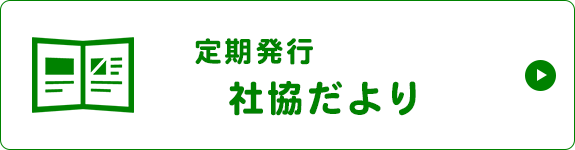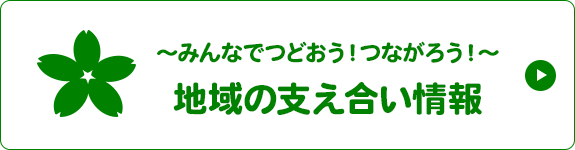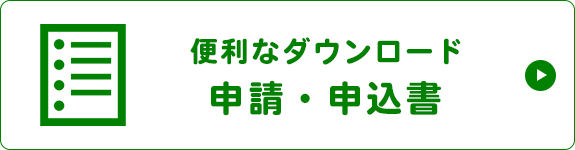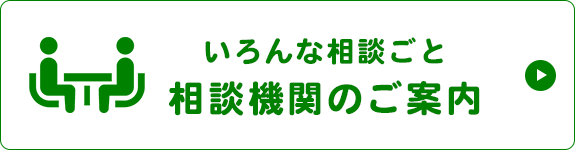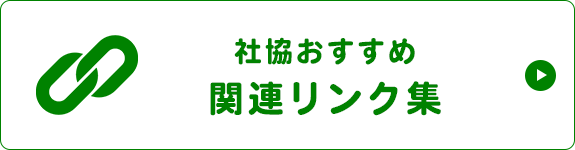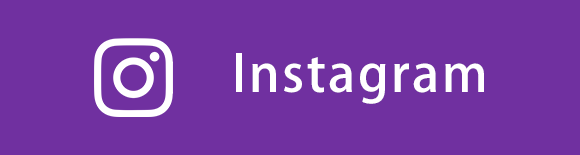活動報告
2016年6月3日 居宅より情報をお届けします(*^_^*)
紫陽花が咲き梅雨の季節となりました。
今年も早くも半分を過ぎようとしています。みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。
今回は、前回の続きで介護、医療、生活支援など地域とのサービスの一体化を図る「地域包括ケアシステム」で医療はどう変わっていくのでしょうか。高齢化で増え続ける医療費を抑えるため昨年、政府は2025年までに病床を減らし医療を必要としていない方々を自宅や介護施設での療養に切り替えるという目標を示しました。
〇病床について
現在、一般病棟・療養病床とわかれていますが2025年までに高度急性期(発病直後に対応した特に高度機能の医療を提供する病院)、急性期(発病後の早期安定へ向けた医療)、亜急性期(在宅復帰支援、慢性期は長期医療の提供)と目的がはっきりと分かれます。

〇「地域包括ケア病床・病棟」の新設
急性期治療を経過し、病床が安定した方に対して、在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行う病棟です。地域包括ケア病棟は、他職種協働型の地域包括ケアシステムを病棟という形にした画期的な病棟でもあります。地域包括ケア病棟の最長退院日数は60日で、回復期リハビリ病棟の180日と比べて短期です。入院費は定額で、リハビリテーション・投薬料・注射料・処置料・検査料・入院基本料・画像診断料等のほとんどの費用が含まれています。しかし一般病棟で行うような高額な医薬品の投与や特殊な検査・手術などには対応できません。
地域包括ケアシステムの目指すところは在宅医療と介護の一体化です。疾病や障がいを抱えても、できる限り住み慣れた地域で必要な医療・介護を受けられるよう各職種がお互いの専門的な知識を活かしながら、チームとなってサポートしていく体制を構築することを掲げています。現実的な社会整備はこれからですが、介護の現実はきれいごとでは回らず抱え込まないことが大切です。。。
介護される側だけではなく、介護する側にも配慮が必要だと思われます。
2016年5月10日 居宅より情報をお届けします(^u^)
新緑の美しい季節となりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
今回は、介護、医療、生活支援など地域との一体化を図る「地域包括ケアシステム」についてお話したいと思います。
団塊の世代が75歳以上(後期高齢者)となる2025年を目途に、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域みんなでひとつになって高齢者の方をケアしていくというシステムです。具体的には住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されると厚生労働省の説明にあります。
これまでは国が主導となって高齢者福祉事業やサービスを行っていましたが、これからは都道府県や市町村など地域が主体となり、支え合い、自主的に行います。
地域包括ケアシステムのポイントとしては2025年までに施設から在宅へ移行していこうとしています。重度の要介護者になっても、なるべく長く、住み慣れた地域、住まいで暮らすことを目指しています。「住まい」を拠点として介護サービスを受けることを基本とし、そのためにも介護の状態に応じて利用できる介護サービスや民間事業所のことを調べておく必要があります。
介護保険法の基本理念は「介護サービスを利用しながら、高齢者が自らの意志に基づき、自らの有する能力を最大限に活かして、自立した質の高い生活を送ることができるよう支援すること」ですが、介護が必要な高齢者の方は医療ケアの必要性も高く、地域包括ケアシステムは、特に医療との一体化がなされてこそ真価が問われるものとされています。
2016年4月7日 居宅より情報をお届けします。
今年は、桜の花も長く楽しむことができました。
ようやく暖かくなり過ごしやすくなってきました。
今回も前回に引き続きまして、『介護予防・日常生活支援総合事業』について説明をしていきたいと思います。
○通所型サービス
①通所介護:現行の通所介護と同様のサービス内容で、生活機能の向上のための機能訓練を行います。既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要な方や集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる方が利用できます。
②通所型サービスA:緩和した基準によるサービスでミニデイサービスや運動・レクレーション等を行います。
③通所型サービスB:住民主体による支援で、体操、運動等の活動など、自主的な通いの場を提供します。
④通所型サービスC:短期集中予防サービスで生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを行います。3~6ヶ月間の短期間で実施します。
訪問介護と同様、今までは、①通所介護であったサービスが、②~④のサービスに移行される可能性があります。全ての方が移行されるわけではありませんが、対象となる方は、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーと相談しながらの移行になっていくと思います。
2016年2月5日 介護予防・日常生活支援総合事業について
寒い日が続き、近年まれにみる大雪が積もりました。
インフルエンザも大流行しているようですので、体調管理にはお気をつけ下さい。
今回は、要支援者に対する多様なサービスを提供するために施行される
『介護予防・日常生活支援総合事業』について説明をしていきたいと思います。
〇訪問型サービス
①訪問介護
訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。
既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要な方や認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う方に対する支援を行います。
②訪問型サービスA
緩和した基準によるサービスで生活援助を中心に行います。
例えば調理や掃除等やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、重い物の買い物代行等を行います。
③訪問型サービスB
住民主体の自主活動として行う生活援助となり、布団干し、階段の掃除、買い物代行や調理、ゴミ出しを行います。
④訪問型サービスC
短期集中予防サービスで保健師等による居宅での相 談指導を行います。
体力の改善に向けた支援が必要な方に対して、3~6ヶ月間の短期間で行います。
⑤訪問型サービスD
移送前後の生活支援で、通所型サービスの送迎や買い物・通院・外出時の支援等、訪問型サービスBに準じて行います。
今までは、①訪問介護であったサービスが、②~⑤のサービスに移行される可能性があります。全ての方が移行されるわけではありませんが、
対象となる方は、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーと相談しながらの移行になっていくと思います。
次回は、通所型サービスについて説明していきたいと思います。
2016年1月6日 居宅より情報をお届けします。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
介護保険は、平成28年4月よりまた、続々と改正が予定されております。まず、今回は、小規模通所介護について説明をしていきたいと思います。
利用定員18人以下(予定)の小規模な通所介護事業所は、
1.地域密着型
志免町に居住されている方は、志免町・須恵町・宇美町・久山町・篠栗町・新宮町にある事業所しか利用ができなくなります。
2.大規模型・通常規模型のサテライト型
元々、同法人内に大規模型・通常規模型の通所介護がある事業所は、職員の勤務体制等が一元的に管理することができるのであればサテライト型に移行することができます。この場合、今まで通り福岡市や粕屋町にある事業所を継続して利用することができます。
3.小規模多機能型居宅介護のサテライト型
小規模多機能型居宅介護のサテライト型は、訪問介護や宿泊サービスを合わせもったデイサービスになりますが、この場合も地域密着型になります。
に移行する予定となっています。
ちなみにデイサービス輝きは、通常規模ですので、変更はありません。
一応、平成28年4月より施行予定ですが、経過措置もあるため、どの型になるのかと移行する時期は、通われている事業所に確認されて下さい。
また、4月より介護予防・日常生活支援総合事業が施行される予定です。
また、情報を随時、流していきたいと思います。